- 順天堂大学医学部附属順天堂医院
- 診療科・部門
- 診療科・外来部門
- 泌尿器科
- 主な治療・手術関連
- 腎がんの薬物療法
腎がんの薬物療法
腎がんの治療は手術療法が第一です。しかし、転移がある方や合併症などのため手術が困難な方の場合は、薬物療法を行います。腎がんの薬物治療には「免疫療法」と「分子標的治療」があります。
薬物療法を行ってもがんを完全になくすことは難しいですが、がんの大きさを小さくしたり、がんの進行を遅らせたりする効果が期待できます。有効な抗がん剤がなく、手術以外の治療法に乏しいと言われてきた腎がんですが、近年、新しい免疫治療薬や分子標的薬が次々と登場したことで治療の選択肢が広がり、患者さん個々の状態に応じた治療が行いやすくなりました。
薬物療法を行ってもがんを完全になくすことは難しいですが、がんの大きさを小さくしたり、がんの進行を遅らせたりする効果が期待できます。有効な抗がん剤がなく、手術以外の治療法に乏しいと言われてきた腎がんですが、近年、新しい免疫治療薬や分子標的薬が次々と登場したことで治療の選択肢が広がり、患者さん個々の状態に応じた治療が行いやすくなりました。
1.進行腎がんに対する治療戦略
進行腎細胞がんに対する薬物療法として、免疫チェックポイント阻害薬(immune checkpoint inhibitor: ICI)とチロシンキナーゼ阻害薬(tyrosine kinase inhibitor: TKI)をベースとした治療が主流となっています。ICIとしては、イピリムマブ、ニボルマブ、ペムブロリズマブ、アベルマブなどが挙げられます。TKIとしては、アキシチニブ、スニチニブ、ソラフェニブ、パゾパニブ、カボザンチニブ、レンバチニブなどが挙げられます。進行腎がんに対する治療には、主に「IMDCリスク分類」というリスク分類に基づき、治療戦略を考えていきます(表1、表2)。例えば、IMDCリスク分類が中・高リスクのグループにおいて、ニボルマブとイピリムマブの併用療法は、スニチニブ単剤よりも全生存率と奏効率が有意に高かったことが報告されています(CheckMate 214試験)。その他、他の病気などで全身状態が悪い患者さん、免疫抑制剤などを使用しているなどICI不適応な患者さんにはTKI単剤を選択することもあります。ここでは、実際に使用される薬剤について解説していきます。表1 IMDCリスク分類
| 血清ヘモグロビン値≦正常値 |
| 血小板数≧正常値 |
| 好中球数≧正常値 |
| 補正カルシウム値≧正常値 |
| Karnofsky performance status*< 80% |
| 診断から全身治療までの期間<1年 |
1〜2個:Intermediate risk (中リスク)
3個以上:Poor risk (高リスク)
*Karnofsky performance status:日常生活でどの程度活動能力があるかを0〜100%までの11段階に分類したもの
表2 進行腎癌に対する薬物一次療法の選択基準
| 分類 | 推奨治療薬 |
| 淡明細胞型腎細胞癌 (低リスク) | ペムブロリズマブ+アキシチニブ併用、ニボルマブ+カボザンチニブ併用、ペムブロリズマブ+レンバチニブ併用、アベルマブ+アキシチニブ併用、スニチニブ、パゾパニブ、ソラフェニブ、(インターフェロン-α、低用量インターロイキン-2) |
| 淡明細胞型腎細胞癌 (中リスク) | イピリマブ+ニボルマブ併用、ペムブロリズマブ+アキシチニブ併用、ニボルマブ+カボザンチニブ併用、ペムブロリズマブ+レンバチニブ併用、アベルマブ+アキシチニブ併用、カボザンチニブ、スニチニブ、パゾパニブ(ソラフェニブ、インターフェロン-α、低用量インターロイキン-2) |
| 淡明細胞型腎細胞癌 (高リスク) | イピリマブ+ニボルマブ併用、ペムブロリズマブ+アキシチニブ併用、ニボルマブ+カボザンチニブ併用、ペムブロリズマブ+レンバチニブ併用、アベルマブ+アキシチニブ併用、カボザンチニブ(スニチニブ、テムシロリムス) |
| 非淡明細胞癌 | スニチニブ、カボザンチニブ、ニボルマブ+カボザンチニブ併用、ペムブロリズマブ+レンバチニブ併用 |
2. 免疫療法
免疫チェックポイント阻害剤は、がんが免疫を逃れて生き延びようとする機構をブロックして、がんに対する免疫によりがんの進行を抑える治療です。これらは免疫治療に分類されるものの、特定の免疫にかかわる分子を標的にする薬剤であり、分子標的薬の一部でもあります。2.1 ニボルマブ (商品名:オプジーボ)

2016年の夏、転移性腎がんもしくは切除不能腎がんに対してニボルマブが日本でも保険適応となりました。これらは、進行腎がんの治療として、長期の効果を期待できる今後非常に期待できるものであります。ニボルマブは、進行悪性黒色腫および進行性肺がん、胃がんなど他のがん種でも治療薬として、広く国内でも使用されています。
がん細胞は、それが増殖する過程において、T細胞などの免疫の攻撃から逃れる能力を獲得します。その一つの機構として、がん細胞は、自らが持つPD-L1という分子とT細胞にあるPD-1という分子と結合させることで、自分を攻撃させないような信号を出し、その結果T細胞からの攻撃を回避します。ニボルマブは、このPD-1に結合して、がん細胞の免疫への回避機構を防ぎ、がん細胞はT細胞に攻撃されることで抗腫瘍効果を示します。
2.1.1 投与方法と通院間隔
ニボルマブは2週間もしくは4週間に1回の点滴治療です。入院でも投与可能であり、通常は4週ごとの通院で、外来化学療法室で投与します。次の項で述べる副作用に対するモニタリングのため、基本的には毎回の採血採尿をお願いしています。また適宜、レントゲン写真やCT検査など画像検査も行ないます。2.1.2 副作用について
この薬剤は免疫機能を上げるため、正常細胞に対する免疫反応が過剰になることがあり、自己免疫疾患のような副作用をきたすことがあります。これらは全身のいろいろな臓器に起こりうるものであり、重篤になる可能性もあります。主なものは、皮膚障害、腸炎(下痢や腹痛など)、間質性肺炎、糖尿病(主に1型といわれるもの)、肝障害、内分泌障害(甲状腺機能低下症など)、腎障害、点滴投与に対するアレルギー反応などがあり、その発症時期もさまざまです。この副作用については、我々医療者側も十分に理解していますが、患者さんご本人やご家族も、それぞれどういった症状が出るのかを知って頂く必要があります。投与開始時にはこの点について、冊子をお渡ししてご説明しますので、起こりうる症状についてご理解頂き、一致するような症状が表れた場合には、連絡頂くか外来受診頂くかで医師や看護師へご相談下さい。また、これらの副作用の可能性のため、今まで自己免疫疾患にかかった既往のある方や、間質性肺炎の治療中、もしくはその既往のある方は治療ができない可能性があります。2.2 イピリムマブ(商品名:ヤーボイ)

イピリムマブが進行腎がんに対する治療として日本で適応されたのは、2018年8月です。この承認により、未治療の進行腎細胞がんに対して、ニボルマブとの併用療法が可能となりました。順天堂では、このイピリムマブ等の免疫チェックポイント阻害剤の治験にも協力し、その有効性と安全性を検証していました。
イピリムマブは、進行性黒色腫や腎細胞癌の治療薬として知られる免疫チェックポイント阻害剤です。がん細胞は免疫系からの攻撃を回避するために、T細胞の活性化を抑制するCTLA-4という分子を利用します。イピリムマブはCTLA-4に結合し、その抑制を解除することでT細胞の活性化を促進し、がん細胞への攻撃を強化します。
2.2.1 投与方法と通院間隔
イピリムマブは通常、3週間に1回の点滴治療として投与されます。投与はニボルマブと併用し、投与期間は3週ごとに4回行われます。イピリムマブ4回の併用療法のあとはニボルマブのみの4週毎の投与となります。治療は外来化学療法室で行われ、投与前後には副作用のモニタリングのための検査が行われます。2.2.2 副作用について
イピリムマブは免疫システムを活性化するため、自己免疫反応が過剰になることがあります。主な副作用には、皮膚障害、腸炎(下痢や腹痛など)、肝障害、内分泌障害(甲状腺機能異常など)が含まれます。これらの副作用は重篤な場合もあり、治療中の継続的なモニタリングが必要です。患者さんやその家族にも副作用について十分に理解していただくことが重要です。2.3 ペンブロリズマブ(商品名:キイトルーダ)

ペンブロリズマブは、PD-1に結合してがん細胞の免疫逃避を防ぐ免疫チェックポイント阻害剤です。ペムブロリズマブが日本で腎細胞癌に対して適応承認されたのは、2020年1月です。この承認は、根治切除不能または転移性の腎細胞癌に対するもので、特にペムブロリズマブとアキシチニブの併用療法が対象となっています。2021年12月には、レンバチニブの併用療法が日本で承認されました。
2.3.1 投与方法と通院間隔
ペンブロリズマブは通常、3週間または6週間に1回の点滴治療として投与されます。外来での治療が一般的であり、治療中は定期的な血液検査や画像検査が行われ、副作用のモニタリングが行われます。2.3.2 副作用について
ペンブロリズマブの副作用は、免疫系の活性化による自己免疫反応が主です。主な副作用には、皮膚障害、腸炎、肺炎、肝障害、内分泌障害(甲状腺機能異常など)が含まれます。これらの副作用は重篤になる可能性があるため、治療中は定期的なモニタリングと患者自身による注意が必要です。2.4 アベルマブ(商品名:バベンチオ)

アベルマブは、PD-L1に結合する免疫チェックポイント阻害剤であり、がん細胞が免疫系から逃れるのを防ぎます。アベルマブは、日本で根治切除不能または転移性の腎細胞がんに対する治療薬として、2019年12月20日に承認されました。この承認は、アベルマブとアキシチニブ(の併用療法に基づいています。
2.4.1 投与方法と通院間隔
アベルマブは通常、2週間に1回の点滴治療として投与されます。内服薬のアキシチニブとの併用療法で使用されます。外来での治療が主であり、治療中は副作用のモニタリングのための定期的な検査が行われます。アベルマブの投与前には、アセトアミノフェンなどのアレルギー反応を予防する前投薬を毎回内服してもらいます。2.4.2 副作用について
アベルマブの副作用も免疫系の活性化による自己免疫反応が主です。主な副作用には、皮膚障害、腸炎、肺炎、肝障害、内分泌障害(甲状腺機能異常など)が含まれます。副作用の発症時期や重篤度は様々であり、治療中の継続的なモニタリングと患者およびその家族の理解が重要です。また他のICI薬剤と比べて、点滴中や点滴後のアレルギー反応(インフュージョンリアクションと言います)が比較的起こりやすいという副作用があります。ただ、この反応はアベルマブ治療を始めたばかりのときに起きやすく、何度か使用すれば起こさなくなります。3.分子標的薬
分子標的薬治療は切除不能、または転移がすでにある腎細胞がんの患者さんが対象になります。分子標的薬は日本では2008年から使用可能となり、チロシンキナーゼ阻害薬とmTOR阻害剤の2つのタイプがあり、現在では合わせて8種類の薬が使用できるようになっています。これらの薬は、腫瘍を小さくしたり、増大を遅らせたりする効果があります。発売開始当時から使用し、現在も治療継続されている患者様もいらっしゃいます。これらの薬は特徴的な副作用が出現することがあるため、当院では分子標的薬の専門外来を設けて治療に当たっています。
3.1 チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)
チロシンキナーゼ阻害剤(TKI)は、がん細胞の成長や拡散を抑えるために使用される薬です。がん細胞が増殖するためには、特定のシグナルが必要です。このシグナルは、体内にあるチロシンキナーゼという酵素によって伝えられます。TKIはこのチロシンキナーゼの働きを阻害することで、がん細胞の増殖を抑えます。3.1.1 ソラフェニブ(商品名:ネクサバール)
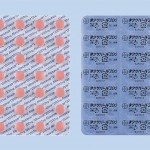
通常1日4錠内服の経口剤です。毎日内服します。手足症候群と言って、手や足の表皮剥離や皮疹ができることが比較的あるため、予防的に角質除去や保湿剤を使用してもらいます。他の副作用は、高血圧、下痢や食欲不振などがあり、稀ですが消化管出血などが起こることがあります。
3.1.2 スニチニブ(商品名:スーテント)

通常1日4カプセルの内服薬ですが、状態に応じて2-3錠から開始することもあります。投与方法は、4週間投与で2週間休薬か、もしくは2週間投与で1週間休薬(2投1休と言います)のサイクルで内服していきます。やや管理が面倒にはなりますが、2投1休の後者の投与方法で主に内服して頂いています。副作用は、血球減少、とくに血小板減少や、手足症候群、倦怠感、甲状腺機能障害などです。消化管出血や心筋障害などの重篤な副作用も稀ですが起こりえます。
3.1.3 アキシチニブ(商品名:インライタ)

通常10mgを2回に分けて内服します。この薬剤は1mgずつ増量減量できるので、副作用と全身状態に応じて個人個人で微調整していきます。毎日内服します。副作用は、蛋白尿が生じることがありますので、1日の尿量を測定してもらい、尿蛋白量を定量することもあります。高血圧も比較的よく起こる副作用です。他には、下痢や食欲不振、疲労感などです。
3.1.4 パゾパニブ(商品名:ヴォトリエント)
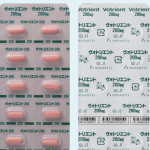
2014年から進行腎がんに対して使用可能となりました。通常4錠の1日1回の毎日内服ですが、食事の直後ではなく、食事の1時間以上前や食後なら2時間は開けて頂いて内服します。副作用に応じて、1日2-3錠に適宜減量することもあります。副作用としては、肝障害があり、生じた場合にはしばらく休薬することもあります。他には、下痢や食欲不振、高血圧や毛色変色などがあります。
3.1.5 カボザンチニブ(商品名:カボメティクス)

国内では2020年から進行腎がんに対して使用可能となりました。カボザンチニブは、1日1回の経口投与で、進行腎細胞がんの治療に用いられます。副作用としては、手足症候群、高血圧、下痢、倦怠感、食欲不振などがあります。特に手足症候群は頻繁に見られるため、予防的な対応が重要です。まれに消化管穿孔や出血などの重篤な副作用が発生することもあります。
3.1.6 レンバチニブ(商品名:レンビマ)

レンバチニブは進行性腎細胞がんの他にも甲状腺がんや肝細胞がんなどの治療に使用されるチロシンキナーゼ阻害薬です。チロシンキナーゼ阻害薬の中では最も新しく、2021年にキイトルーダとの併用療法として国内で承認されましたので、単剤では使用できず、必ずキイトルーダとの併用療法で開始します。この薬は複数の受容体チロシンキナーゼ(RTKs)を阻害することで、腫瘍の成長と血管新生を抑制します。 レンバチニブは経口薬で、通常1日1回、空腹時に服用します。治療は外来で行われることが多く、定期的な血液検査や画像診断を通じて治療効果と副作用のモニタリングが行われます。
副作用としては高血圧が頻繁に見られる副作用であり、降圧剤の使用が必要となることがあります。その他蛋白尿、疲労感、下痢、手足症候群、肝機能障害、食欲不振などがあり、服用量は患者さんの状態や副作用の出現状況に応じて調整されることがあります。
3.2. mTOR(エムトール)阻害剤
3.2.1 エベロリムス(商品名:アフィニトール)

通常1日2錠の内服薬で、副作用の強くない限りは休薬せず毎日使用します。最も多い副作用は、口内炎であるので、予防的にうがい薬などを使用して頂いております。間質性肺炎は副作用としても重篤になりえるため、間質性肺炎マーカーや胸部レントゲンによる定期チェックが必要です。咳や発熱、呼吸苦が出た場合は、すぐ受診して頂くか、休薬して下さい。またこの薬剤は、免疫抑制剤として使用されることもあるので、易感染性をきたすことがあり、肝炎のキャリアなどがあるとすぐには使用できません。他には腎機能障害や血球減少などがあります。
3.2.2 テムシロリムス(商品名:トーリセル)

週に1回の点滴投与の薬剤です。通常は週に1回外来で投与します。アレルギー反応が出るのを抑えるために、事前に抗アレルギー剤を内服するか、投与前に抗アレルギー剤を点滴で入れてから使用します。副作用は、エベロリムスと同様に間質性肺炎があり、重篤になる可能性もありますので、呼吸器症状が出たら受診して下さい。また免疫低下作用を有するため、口内炎や易感染性も同様にあります。腎障害や血球減少も起こりうる副作用です。
4. 費用について
分子標的薬も免疫チェックポイント阻害薬もかなり高額な薬剤です。通常1ヶ月で15万円程度の費用がかかります。現在外来通院でも高額療養費制度が使用可能であり、それを使用すれば自己負担額はその他検査費用なども含めて、患者さんの収入に応じてですが、8万円程度の上限額に調整されます。また、併用療法はさらに高額ですが、高額療養費制度や限度額適用認定などの手続きが利用できますので、費用についてご不明な点は支援センターなど各相談窓口へご相談下さい。5.専門外来のご案内
分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は特徴的な副作用があり、それにうまく対処しながら、なるべく長期間使用していく必要があります。ほぼ受診毎に診察前に採血採尿をお願いしており、適宜胸部レントゲン写真やCTなど画像診断も行ないます。副作用のマネジメントで併用薬が多くなる傾向にありますので、順天堂医院では専門外来を設けており、専門的に対処させて頂いております。分子標的薬外来
毎週月曜日午後13時〜 予約制
担当 永田政義
文責:小林拓郎 永田政義
毎週月曜日午後13時〜 予約制
担当 永田政義
文責:小林拓郎 永田政義